文化財紹介
更新日:2025年1月27日
清須市指定文化財
清須市では29件の文化財が清須市指定文化財に指定されいます。
問屋制札(とんやせいさつ)教育委員会蔵 清須市指定文化財第7号
大きさ
94cm×40cm×2.5cm
説明
「問屋制札」は、宝暦六年(1756年)の「市場定法(いちばじょうほう)」を記したもので、江戸時代の「株仲間」(問屋)が持つ特権の一端を物語る貴重な資料です。
展示場所
清須市西枇杷島問屋記念館で展示しています。
市場定法
営業時間、商い方法など4ヶ条が書かれています。
株仲間
江戸時代、藩に運上金を納めることによって市場での物の売買に独占的な権利を認められた同業組合のこと。
美濃路道標(みのじどうひょう)教育委員会蔵 清須市指定文化財第8号

大きさ
高さ173cm、一辺31cmの御影石でできた石柱
説明
文政十年(1827年)、旧枇杷島橋の小橋のたもとに立てられました。旧枇杷島橋は、名古屋五口の一つ「枇杷島口」にあたり、小橋を渡ったところで西に美濃路(みのじ)、北に岩倉街道(いわくらかいどう)が伸び、両街道の分岐点でした。四辺の各面には、
東 にしは、つしまてんのうきよす宿みち
西 ひがしは、とうかいどうなごや道
南 文政十年丁亥七月吉日
北 いわくら道
と刻まれています。
場所
清須市内の「市場モニュメント」脇に立っています。
二松学校校名額(ふたまつがつこうこうめいがく)教育委員会蔵 清須市指定文化財第9号

大きさ
横175.6cm、縦73.1cm、厚さ3.1cm。
説明
桧(ひのき)の一枚板で、明治28年(1895年)につくられたものです。二松学校は、現在の西枇杷島小学校の前身にあたり、明治9年(1876年)に、「清成学校(せいせいがっこう)」を「二松学校」と改称し、新築になったことにより始まりました。
額面には「二枩學黌(ふたまつがつこう)」と校名が横書きされ、その左に「正三位勲一等 井上毅(しようさんみくんいつとう いのうえこわし)」と筆者の名前が記されています。
井上毅
いのうえこわし(1839年-1895年)は、明治政府の官僚で、明治26年3月から8月まで第二次伊藤博文内閣の文部大臣を務めました。
水野千右衛門(みずのせんのえもん)の陳情書 個人蔵 清須市指定文化財第10号
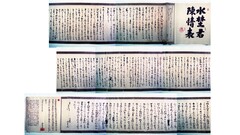
説明
新川開削工事の普請奉行であった水野千右衛門が、工事の予算超過の責任を問われて降職、謹慎させられました。謹慎中の身でありながら、尾張藩主宗睦(むねちか)に提出した陳情書の下書き。陳情書は自分の信念及び工事方法、今後の治水対策などについて書かれています。工事は続行され、天明7年(1787年)に完成しました。
西枇杷島町小学校のクロガネモチ 清須市指定文化財第11号

大きさ
樹高9.8m、幹回り2.03m
説明
大正四年(1915年)、現在の場所に西枇杷島小学校が開校して以来、約80年にわたり、ずっと子供たちの成長を見守りつづけています。学窓(がくそう)をともにした多くの師弟の目に触れ、現在まで親しまれ、思い出に結びつく記念物として貴重なものです。樹齢不明。
場所
西枇杷島小学校校庭
小場塚弁財天縁起版木(こばつかべんざいてんえんぎはんぎ)小場塚氏子蔵 清須市指定文化財第12号
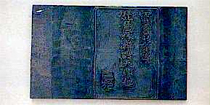
大きさ
縦30.5cm、横18cm(全5点)
説明
嘉永七年(1854年)、市寸島神社(旧琵琶塚弁財天)の再建にあたり、神社の由来を琵琶悲恋物語とともに記述し、版行したものです。
明治十一年(1878年)に市寸島神社となる以前は、弁財天社とか市杵嶋姫命社(いちきしまひめみことしや)と称され、版木は氏子の方々によって大切に保存され、現在に至っています。
展示場所
展示はしていません。
三尊釈迦如来像(さんぞんしゃかにょらいぞう)渡河山西方寺蔵 清須市指定文化財第13号
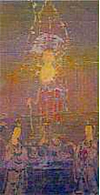
大きさ
縦120cm、横60.8cm
説明
西方寺が天台宗であった時の本尊と伝承され、収納箱には「釈迦如来唐張思恭筆(しゃかにょらいとうちようしきようしつ)」とあります。中尊と両脇侍が踏割蓮華座に直立しています。台座の下には飛雲があり、今まさに来迎したばかりの情景が描かれています。最近の研究によれば「阿弥陀三尊来迎図」とも考えられています。中国宗時代の作。
本図は俊乗房重源(しゆんじようぼうちようげん)が宗の文化を移入して日本に再現するにあたり、宗仏画を用いた実例として、またわが国の鎌倉時代の芸術に与えた影響やその受け入れを表わすことができる貴重な資料です。
保存場所
渡河山西方寺(清須市西枇杷島町小田井三丁目11番地1)。毎年虫干し時に見学可能です。
光明本尊像(こうみようほんぞんぞう)渡河山西方寺蔵 清須市指定文化財第14号

大きさ
縦155.7cm、横60.8cm
説明
本図は絹本着彩(けんぽんちゃくさい)で、中央に八字名号「南无不可思議光仏(なむふかしぎこうぶつ)」という光明本尊が描かれています。この作品の特徴は、「无」の字を用いていることや、光条が四十条と数多いことなどがあげられます。
制作は、室町時代初めと認められ、保存は極めて良好で、明快な色調とも相まって本図の絵画的な価値を高めています。
保存場所
渡河山西方寺(清須市西枇杷島町小田井三丁目11番地1)。毎年虫干し時に見学可能です。
髪繍阿弥陀如来像(はつしゆうあみだにょらいぞう)亀岳山宝国寺蔵 清須市指定文化財第15号
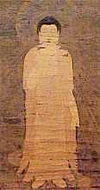
大きさ
縦108cm、横39.3cm
説明
蓮華座に立った阿弥陀如来が雲に乗り、見る者に対して真正面に来迎(らいごう)してくる様子をあらわしています。
本図は、鎌倉時代の作と確認されたもので、絹本着彩(けんぽんちゃくさい)、如来の頭髪部は髪繍(はつしゆう:髪の毛で刺しゅうされているもの)されています。
保存場所
亀岳山宝国寺(清須市西枇杷島町小田井一丁目7番地2)
旧枇杷島橋・小橋橋柱(こばしきようちゆう)教育委員会蔵 清須市指定文化財第16号

大きさ
高さ155cm、一辺48cmの石柱
説明
明治20年(1887年)に枇杷島小橋は建てられました。橋名の「枇杷島小橋」は、井村常山(から1925年)の書で、彫刻は梅吉と記録されています。 大正元年(1912年)、枇杷島橋が現在の県道位置へ移動したのにともない、当時、中島にあった郡役所へ移されました。その後、中小田井の旧家に引き取られ庭石として保管されてきましたが、平成5年5月に移されました。
年中行事弐冊目(ねんちゅうぎょうじにさつめ)問屋町町内会蔵 清須市指定文化財第18号
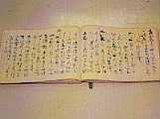
大きさ
縦18.8cm、横14.8cm、176ページ
説明
弘化四年(1847年)より安政四年(1857年)の問屋町の町内行事が書かれています。問屋町の山車・頼朝車の修復に係わる金銭的負担、仕事の遅れなどの町人の苦労を始め、当時の町人の生活・宗教感・風習や習慣をうかがい知ることのできる貴重な資料です。
尾張藩拝領太鼓(はいりょうたいこ)問屋町町内会蔵 清須市指定文化財第19号

大きさ
直径31cm、厚さ5.5cm、太鼓吊り(60×60×3.3cm)
説明
天保二年(1831年)、祭り好きの殿様として知られる尾張藩10代藩主・斎朝(なりとも)公が、枇杷島祭りを上覧した際、拝領しました。太鼓を包む風呂敷に「新御殿(しんごてん)・御小納戸役所(おんなんどやくしょ)・役懸り(やくかかり)」と記されています。また、太鼓吊りには、立派な蒔絵(まきえ)が施されています。
蒔絵
漆塗り(うるしぬり)の器物の面に、種をまくように金銀粉で絵模様を描く。
小川伝七家文書(おがわでんひちけもんじょ)教育委員会蔵 清須市指定文化財第20号

大きさ
縦25.5cm、横18cm、七分冊全117枚
説明
天保13年(1842年)の株仲間解散による問屋閉鎖から、安政5年(1858年)の問屋再開までの16年間に、藩の役所へ提出した願書の下書きや写しなどからなり、この間の問屋の動向が記録されています。下小田井の市の三百余年という長いあゆみの中でも、最も激動期といってもよい時期の問屋の様子をうかがい知ることのできる貴重な資料です。
枇杷島市場開設命令書 個人蔵 清須市指定文化財第21号
説明
明治42年(1909年)12月に枇杷島市場問屋業組合が、愛知県に市場の開設を出願した申請に対して同43年1月に認可された「命令書」付許可証。この資料は江戸時代初期から230年続いてきた問屋が、明治の近代国家へ移り変わる中で大きく体質改善を余儀なくされたことを物語る資料です。
枇杷島市場規程(びわじまいちばきてい)教育委員会蔵 清須市指定文化財第22号
大きさ
説明
明治43年(1910)、当地において結成された「枇杷島市場問屋業組合」が作成し、枇杷島市場の各問屋の店先に掲げられていたものです。全27ヶ条からなり、「市場の意義」から「市場規程掲示」や「ごみの処理」など細かく規制されています
展示場所
清須市西枇杷島問屋記念館で展示しています。
渡辺家文書(わたなべけもんじょ)教育委員会蔵 清須市指定文化財第23号
大きさ
説明
下小田井村の庄屋であった渡辺伊蔵が在職期間である天保15年(1844年)から嘉永6年(1853年)に残した文書。文書の内容は、年貢の減免願いや土地の売買、凶作・飢饉、災害に関することなど多岐にわたっています。また、免定(年貢割付状)から当時の免相(課税率)や石高の推移なども明らかになり、当時の生活をうかがい知ることのできる資料です。
近藤家文書(こんどうけもんじょ)個人蔵 清須市指定文化財第24号
大きさ
説明
小場塚新田の庄屋職を務めた伝左衛門家に伝えられた慶安年間から明治期までの文書。この文書は免定が開村以来200通あまりがほぼ欠けることなく残されています。また、免相(課税率)の推移から新川が水害対策に効果を発揮していたことがわかりました。なお、明治期に関しては、明治8年(1875)から同19年(1886年)までの布告集等が残されています。
五条川右岸収穫図(ごじょうがわうがんしゅうかくず)清須市指定文化財第25号

大きさ
縦162.5cm×横169.6cm
説明
明治3年に下之郷村(現清須市春日地区)に生まれた日本画家、丹羽有芳の作品。
昭和5年から10年の五条川沿岸の様子を描いた屏風絵で、近隣に住む実在の夫婦を描いた珍しい作品である。
夏渓水禽図(かけいすいきんず)清須市指定文化財第26号

大きさ
縦144.0cm×横71.5cm
説明
同じく丹羽有芳の作品。
明治43年に新古美術展覧会に出品した作品で、展覧会に出品したものでは現存する最古の作品である。ノウゼンカズラの花と水鳥を配した、有芳画得意とする花鳥画の初期作品である。
朴樹小禽図(ぼくじゅこきんず)清須市指定文化財第27号

大きさ
縦134.4cm×横59.4cm
説明
同じく丹羽有芳の作品。
旧派の画家である有芳が「たらしこみ」といわれる新派の技法を用いた注目すべき作品である。この作品には裏書があり、「昭和元年六月初旬法瑞寺境内之朴樹ニ雀ヲ配置シテ写生ス」と記されている。法瑞寺とは有芳の菩提寺で、現春日地区冨士塚にある浄土真宗の寺である。
僧形合掌像(そうぎょうがっしょうぞう)清須市指定文化財第28号

大きさ
像高50.5cm
説明
江戸初期に全国を行脚しながら12万体の仏像を彫ったとされる、円空作のいわゆる「円空仏」である。
僧が合掌した形の珍しい像で、円空最盛期の延宝初期(1675年頃)の像造と考えられます。
お問い合わせ
教育委員会事務局 教育部 生涯学習課
清須市役所南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
